・・・・なんだ、みんなのりが悪いぞー。この掛け声を聞いたらすかさずジャンケンしなくちゃ。それが日本人ってもんだろー。先生みたいな日本蛙だって、すでに条件反射としてすりこまれてるくらいだからねー。はっはっは。もっかいやるぞー!じゃぁん けぇん ほいっ!・・・誰もやらないなぁ。なぜだー?恥ずかしがることはないぞー。先生と君たちの仲じゃないかもしれないかもしれないじゃないかー。はっはっは。まあいいや。
とにかく、今日、ジャンケンから入ってみたのはね、このジャンケンに関係が深い映画をとりあげちゃおーと思ったからなんだよ。なぜ?って理由なんかあってないようなモンテスキューは三権分立、蓼喰う虫は好き嫌いが激しいってなわけです。わからない?いーんだよ。先生のね、エスプリは後で効いてくるから。きっとね、後、そーだなー。10年ぐらいして、ふと空を見上げた時の雲の形が先生の顔に見えたりしてね、そんなときに、ああ、あれはそーゆーことだったか、っとね、効いてくるんです。ホントに。だから、黙って聞きなさい。はっはっは。
で、ジャンケンの話に戻るんだけどね、ジャンケンってのは、改めてゆーほどのことでもないだろーけど、パーはグーに勝ってグーはチョキに勝って、チョキはパーに勝つとゆー、三すくみを利用した勝負なわけだ。だから、グーチョキパーでなくても、何か、三すくみの構造をもつものに置換えても、ジャンケンってのは当然成立するねー。あたり前だねー。極端な話、A、B、Cの三つを表す記号と、その優劣関係が円になるように決められたルールさえあればいいわけだからねー。はっはっは。だから、当然、事実として、ジャンケンにもいろんなバージョンがあったんだよね。どちらかとゆーと、ジャンケンは江戸末期以降に出てきた新参者で、文献に最初に出てくるのも「誹風柳多留」の156巻で、「リャン拳て鋏を出スハ花屋の子」って川柳なんだって。これが天保9年だから、江戸の末期だねぇ。「庄屋」と「猟師」と「狐」を使った「狐拳」とか、「和籐内」「虎」「和籐内の母」を使った「虎拳」とかね、その辺が、江戸時代の流行だったよーだねー。
そんな、ジャンケンのバリエーションの中で、最も歴史が長いのは、中国から平安時代には伝わっていたといわれる「虫拳」なんだ。ちょっとね、高度な授業でしょ。先生もね、無理してみました。はっはっは。虫拳は、蝦蟇と蛇と蛞蝓(なめくじ)の三すくみを使ってるんだよ。出た!蛙がでました!時間かけすぎ?そーかもしれんね。はっはっは。親指を出すと「蝦蟇」、人差し指で「蛇」、小指で「蛞蝓」。不本意ながら、蛇が蝦蟇に勝つのはしょーがない。先生も蛇は苦手ですねー。鰻なら喰えるんだけどねー。蒲焼うまいよ。あの香りがもうね、漂ってくるとたまらんね。ああ・・・・食べたいなあ・・・。重じゃなくて丼、上じゃなくて並でいいんだけどなー・・・誰かおごってくんない?だめ?先生が与える素晴らしい知識の代償をここで一発払おうという気にはなりませんかねー。え?給料もらってんだろう?いやまあ、薄給ですよ。薄給にかける情熱。薄給だけに意識を集中すればこれがだんだん大きく見えてくるんだ。それをバットで振れば、全部ホームランてわけさっ、ああ、今先生は、三振する気がしない。風を感じるんだ。さわやかな風をね。はっはっは。
蛇は蝦蟇に勝つと。蝦蟇は蛞蝓に勝つ。ここまでは、イメージとしてよくわかるんだけどね。蛞蝓が蛇に勝つってのはどーだろーね?すっきりしないなぁ。まあ、蛇は蛞蝓の通った跡を避けるというような説明がされてるのもあるんだけどねー。勝ち負けとしてはどーなんだろ。漢籍に出典があるようだけど、もとは実は蛞蝓じゃなくて、百足だったって話もあるんだけどね、百足でもスッキリしない感が残るねー。ん?スッキリしないってのは、何かが残ってるからで、「スッキリしない感覚が残る」という表現は同語反復だ?いーんです。そんなことは。先生はロジックより感性を大事にする蛙だからねー。はっはっは。いや、専門は数学だよ。数学はロジックだけどね。感性数学を目指してるわけだ。こら、「山勘数学」って言ったの誰だー!
続けるぞー。この、虫拳の三すくみ構造を、お話の中に取り込んだのが、美図垣笑顔作の江戸時代の読本「児雷也豪傑譚」。主人公の児雷也は、「自来也」とも書くんだけど、ああ、そういえば、「磁雷矢」って書くのもあったねー。「世界忍者戦ジライヤ」。なんじゃそりゃ、って言われてもね、城忍フクロウ男爵は、英語まじりの日本語をしゃべるんだけど、なんか、英語が下手、ってところが一番印象に残る番組だよ。知らない?知らないかー。はっはっは。
そんな世界忍者はともかく、児雷也っていうのは、もともとは、中国のね、「我来也」ってゆーね、盗みに入った家に、「我来るなり」と書き残していく、盗賊がモデルだって言われてんだ。だから、児雷也も、義賊って設定。忍者じゃないよ忍者じゃ。でも、さっきの磁雷矢にしろNARUTOのジライヤにしろ、カクレンジャーのジライヤしろ、みんな忍者だねー。盗賊ではないねー。はっはっは。別にいいけど。
ポイントは、この児雷也、蝦蟇の妖術が使えるってこと。蝦蟇の妖術をね、使うといえば、浄瑠璃「傾城島原蛙合戦」の七草四郎とか、天竺徳兵衛とか、そんなんが思い浮かぶけどね、まあそういった、大蝦蟇の妖術を使うキャラクターなわけだ。え?大事なのを忘れてる?そうか?言ってみろー・・・・ああああああああ、あったねええぇぇぇぇぇぇっ、忍者じゃじゃ丸くん!!
先生もね、ファミコンに熱中した世代として懐かしい限りだなぁ。はっはっは。ところで、君いくつ?まあいいけど。
児雷也ものは、時代にしろ、主人公の背景にしろ、色んな設定があって、バラバラなんだけど、一貫している設定としては、もとは由緒ある家柄で今は没落、御家再興を目指して義賊をしている、ってところと、仙素老人に蝦蟇の妖術を授けられるところかな。あと、主人公らしく、眉目秀麗な若者ってことになってる。で、この児雷也の話に、蛇の妖術を使う大蛇丸と、蛞蝓の妖術を使う綱手姫を絡めて、蝦蟇、蛇、蛞蝓の三すくみを実現させたのが、「児雷也豪傑譚」なわけだねー。眉目秀麗な蝦蟇使いなんて、まるで先生みたいだねー。先生の場合は、眉目秀麗な蛙先生だけどねー。眉はないけど。はっはっは。じゃあ、どんなに眉目秀麗か、杉浦茂の漫画「少年児雷也」から見てみよう。はい、これ!

・・・蛙の絵がねえ。いい加減だよ・・・・。
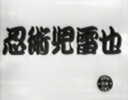 さあ、気を取り直して、映画の話にゆこうじゃないか。おどろーじゃないか。さわごーじゃないか。こんな設定があれば、大スペクタクル映画ができちゃうと思うだろ。思おうじゃないか。その日本映画界に燦然と輝く特撮映画こそ「忍術児雷也」!!拍手拍手はくしゅーぅぅぅぅぅぅぅ。
さあ、気を取り直して、映画の話にゆこうじゃないか。おどろーじゃないか。さわごーじゃないか。こんな設定があれば、大スペクタクル映画ができちゃうと思うだろ。思おうじゃないか。その日本映画界に燦然と輝く特撮映画こそ「忍術児雷也」!!拍手拍手はくしゅーぅぅぅぅぅぅぅ。舞台は室町末期から戦国時代ぐらい。応仁の乱以後、世が乱れているなか、更級城の尾形家は、越後の鯨波家と信州の諏訪家の陰謀により滅ぼされ、鯨波は、尾形家再興のため、山々にこもる尾形の残党を討伐することに躍起になっていたってところがナレーションで解説される。
そして、鯨波家の城。尾形の残党のうち、家老格の大物宮原兵衛が見つかった、という情報がもたらされる。城主は、すぐに討伐隊を向かわせようとするが、その地方の百姓の信頼も厚い彼らを、鯨波家が討つのは得策ではない、という家臣の意見を入れ、土豪というか、山賊のような生活をしている、願人太郎に、残党狩りを依頼する。
願人太郎は、同じく山を支配している大蛇太郎と針木太郎を呼び寄せ、一緒に残党狩りをすることを提案するが、針木太郎はこれを辞退する。実は、彼は、尾形の残党の一人だったわけだ。針の木太郎の様子に疑問を持った願人太郎は彼に尾行をつけて、その秘密を知ってしまい、針木太郎を襲う。
場面変わって、尾形の残党の集落。家老格の老人が発作を起している。どーやら子供、といっても大人なんだけど、兄妹がいて、兄は周馬、妹は深雪という名前らしい。この兄が主役だね。ちょっと顔が間抜けて見えるんだけど。はっはっは。父親の発作に、慌てて町まで薬を取りに行く周馬。
 一方で針木太郎は何とか自分の山に逃げ帰る。その山には、尾形家の跡取りの許嫁であった綱姫が匿われていた。宮原兵衛が襲われることを知った綱姫は、ただちに救援へ向かう。
一方で針木太郎は何とか自分の山に逃げ帰る。その山には、尾形家の跡取りの許嫁であった綱姫が匿われていた。宮原兵衛が襲われることを知った綱姫は、ただちに救援へ向かう。駆け付ける途中、大蛇太郎らの一団に行く手を阻まれ、矢を当てられて乗っていた馬が暴走し、綱姫は崖下に落ちてしまう。あと、針木太郎は捕えられる。
その頃、願人太郎は宮原兵衛の村を襲撃しており、宮原兵衛は切られ、深雪はさらわれてしまう。そして、一体どんな遠くまで薬を買いにいったんだかこの騒ぎに気が付かないとは一体どういうことだ周馬君は、全部が終わって、皆居なくなったところに、ちょうどよく帰ってくる。
 切られて今にも力尽きそうな父を見つけ、駆け寄ると、父と思っていた宮原兵衛は、「私はあなた様の本当の父親ではありません。あなた様は、尾形家当主尾形弘澄様の忘れ形見、周馬弘行様です。」と、周馬の本当の身分を明かして、そのまま息をひきとった。周馬は旅にでる。
切られて今にも力尽きそうな父を見つけ、駆け寄ると、父と思っていた宮原兵衛は、「私はあなた様の本当の父親ではありません。あなた様は、尾形家当主尾形弘澄様の忘れ形見、周馬弘行様です。」と、周馬の本当の身分を明かして、そのまま息をひきとった。周馬は旅にでる。 一方、崖下に落ちていた綱姫は、老婆に変身できるナメクジなのか、ナメクジに変身できる老婆なのか、そこんとこはよくわかんないンだけど、とにかく、不思議な老婆に救われて、ナメクジの妖術を授かる。願人太郎と大蛇太郎は、戦勝の祝いをしている。女好きの大蛇太郎は、さらってきた深雪に乱暴しようと、外に連れ出すが、そこに居合わせた、諏訪家家臣の遠山弓之助、これがね、かの若山富三郎のデビューなんだけどね、あ、興味ない?いかんなー。若山富三郎を知らんとは。勝新太郎は知ってンの?中村玉緒の旦那?一体どーゆー知識だろーねーそれは。勝新太郎の兄貴です。覚えとくよーに。試験に出るよ、数学の。はっはっは。ああ、そうそう、その遠山弓之助に邪魔されてね、深雪は逃げるんだ。
一方、崖下に落ちていた綱姫は、老婆に変身できるナメクジなのか、ナメクジに変身できる老婆なのか、そこんとこはよくわかんないンだけど、とにかく、不思議な老婆に救われて、ナメクジの妖術を授かる。願人太郎と大蛇太郎は、戦勝の祝いをしている。女好きの大蛇太郎は、さらってきた深雪に乱暴しようと、外に連れ出すが、そこに居合わせた、諏訪家家臣の遠山弓之助、これがね、かの若山富三郎のデビューなんだけどね、あ、興味ない?いかんなー。若山富三郎を知らんとは。勝新太郎は知ってンの?中村玉緒の旦那?一体どーゆー知識だろーねーそれは。勝新太郎の兄貴です。覚えとくよーに。試験に出るよ、数学の。はっはっは。ああ、そうそう、その遠山弓之助に邪魔されてね、深雪は逃げるんだ。 旅に出ていた周馬は、山の中で、巨大な蝦蟇と大蛇が対決してる場面に出くわす。対決とはいってもね、何か、見るからにぬいぐるみ、って感じの蛇と蛙がね、たいして動くこともなく、白い煙りをどっからともなく吐いている、っていう、迫力いま一つの対決なんだけど、蛇が嫌いだったのか何なのか、周馬は持っていた短筒で大蛇を撃ち、蝦蟇を助ける。
旅に出ていた周馬は、山の中で、巨大な蝦蟇と大蛇が対決してる場面に出くわす。対決とはいってもね、何か、見るからにぬいぐるみ、って感じの蛇と蛙がね、たいして動くこともなく、白い煙りをどっからともなく吐いている、っていう、迫力いま一つの対決なんだけど、蛇が嫌いだったのか何なのか、周馬は持っていた短筒で大蛇を撃ち、蝦蟇を助ける。 助けられた蝦蟇は老人にかわり、周馬に礼を言うが、すでに蛇との闘いで力を使い果たした蝦蟇の精は、周馬に蝦蟇の妖術の極意を記した巻き物を授けると、そのまま息を引き取る。あああ、この巻き物欲しーぃぃぃぃ。欲しいだろ?欲しくない?どーして。蝦蟇の妖術だよ蝦蟇の。ただね、先生みたいな蛙が蝦蟇の妖術を使うとどうなんのか、その辺に不安は残るけどね。はっはっは。で、逃げていった大蛇は、大蛇太郎に憑りつき、大蛇丸となる。
助けられた蝦蟇は老人にかわり、周馬に礼を言うが、すでに蛇との闘いで力を使い果たした蝦蟇の精は、周馬に蝦蟇の妖術の極意を記した巻き物を授けると、そのまま息を引き取る。あああ、この巻き物欲しーぃぃぃぃ。欲しいだろ?欲しくない?どーして。蝦蟇の妖術だよ蝦蟇の。ただね、先生みたいな蛙が蝦蟇の妖術を使うとどうなんのか、その辺に不安は残るけどね。はっはっは。で、逃げていった大蛇は、大蛇太郎に憑りつき、大蛇丸となる。場面変って針木太郎が処刑されるシーン。あわや、というところで、綱姫が登場、薙刀を振り回して針木太郎を救い出し、妖術で川を渡って逃げのびる。
鯨波家の屋敷では、針木太郎を逃がしたことで、担当者が叱責されている。怒鳴りまくっているその上司らしき人物が、ふと、見なれない腰元がいることに気が付く。問いただすと新しく入った者だという。そして、鯨波家当主鯨波照忠の間。新しく入った腰元が踊りを披露するという。しばらく踊っていると、突然の煙とともに女は、槍を構えた尾形周馬改め児雷也に変わる。名乗りをあげて、照忠に迫る児雷也。
 鯨波家の家来に囲まれるが、少しも慌てず、そのまま庭へ。そこで姿を消したかと思うとあっという間に城の屋根の上に登ってしまう。火縄銃で狙われるが、雨を降らせ、「命を取るのはたやすいが、尾形家の無念を思って、すぐには取らない。これからは枕を高くしては寝られない。」との脅しをかけて、そのまま雲に乗って去ってしまう。普通こういうのは悪人の台詞だよ。「罪を憎んで人を憎まず」というヤットデタマンの大巨神のような精神で望んでほしーもんだよね。ヒーローは。はっはっは。
鯨波家の家来に囲まれるが、少しも慌てず、そのまま庭へ。そこで姿を消したかと思うとあっという間に城の屋根の上に登ってしまう。火縄銃で狙われるが、雨を降らせ、「命を取るのはたやすいが、尾形家の無念を思って、すぐには取らない。これからは枕を高くしては寝られない。」との脅しをかけて、そのまま雲に乗って去ってしまう。普通こういうのは悪人の台詞だよ。「罪を憎んで人を憎まず」というヤットデタマンの大巨神のような精神で望んでほしーもんだよね。ヒーローは。はっはっは。今度は、諏訪家の氏神らしい「諏訪大社」の参道。諏訪家のまだ幼い若君と、鯨波家との婚礼が決まっているという姫君が参拝に来ている。それを見ていた願人太郎と大蛇丸。女好きの大蛇丸は、諏訪家の姫に目をつけて、手下を使って参拝の帰りを襲わせる。
 連れ去られそうになるところに駆け付けたのが、綱姫改め綱手と針木太郎。姫と若君を救って諏訪家の屋敷に入る。実は諏訪家では、その昔、鯨波家とともに尾形家を撃ったことを後悔しており、尾形家再興に協力しようと考えていたんだ。そこに、姫を気に入った大蛇丸が忍び込む。大蛇の姿になったものの、蛇の嫌いな蛞蝓の妖術を使う綱手がいたことで、大蛇丸は退散する。三すくみですねー。はっはっは。綱手と針木太郎は諏訪家の考えを知り、諏訪家の協力で尾形家再興を目指すことにする。
連れ去られそうになるところに駆け付けたのが、綱姫改め綱手と針木太郎。姫と若君を救って諏訪家の屋敷に入る。実は諏訪家では、その昔、鯨波家とともに尾形家を撃ったことを後悔しており、尾形家再興に協力しようと考えていたんだ。そこに、姫を気に入った大蛇丸が忍び込む。大蛇の姿になったものの、蛇の嫌いな蛞蝓の妖術を使う綱手がいたことで、大蛇丸は退散する。三すくみですねー。はっはっは。綱手と針木太郎は諏訪家の考えを知り、諏訪家の協力で尾形家再興を目指すことにする。しかし、そのことをしらない周馬は、諏訪家に復讐するため諏訪家に入り込み、若君を誘拐しようとする。大蝦蟇に変身して城を出て行こうとするんだけど、この大蝦蟇がなんとも歩くのが遅くて、変身しないほうがましなんじゃないかという状態。出口のところで、大日坊という山伏みたいな人が立ちふさがって、周馬の術をあっさり破り、周馬は逃げ出す。大日坊は、諏訪家に妖術を破る宝刀「朝霧丸」を授ける。 大蛇丸と願人太郎は鯨波家に入り込み、用心棒を買って出る。街に出て遊ぶふたりが入った店に偶然深雪が居合わせ、願人太郎は彼女をさらっていく。
大蛇丸は、酔った勢いでもう一度諏訪家に入り込むが、今度は朝霧丸を持った高遠弓之助に阻まれてしまう。一方、深雪をさらってアジトに帰ろうとしている願人太郎の前には、針木太郎が立ちふさがる。しかし、多勢に無勢で押しまくられ、崖の上から転落してしまう。さらに追い討ちをかけようとする願人太郎の手勢が崖を降りていくと、そこには周馬大蝦蟇がいて、針木太郎を助ける。願人太郎は大蛇丸のアジトに駆け込み、周馬はその後を追う。そして、最後の戦いということになりますなー。
 当然雑魚はいてもいなくても同じ。ポイントは大蛇丸と周馬の争い。大蛇丸対周馬戦が、チャンバラで行われているところに、雑魚対応ということで針木太郎らが攻め込む。大蛇丸と周馬は、最後、大蝦蟇と大蛇に変身して対峙するんだけど、当然、三すくみの構造からいって、主人公が危うくなっちゃう。そもそもライバルに構造的に勝てない主人公というのもどうかと思うんだけどね、ああもうだめだ、ってところで綱手がやってきて、3匹そろい踏み。三すくみっていったって、そのうち2つが手を組んでいればね、とりあえず相手は退散するしかないでしょう。大蛇丸は逃げ出す。主人公カッコ悪ー。悪悪だね。もう。この手の映画としては致命的ですな。はっはっは。
当然雑魚はいてもいなくても同じ。ポイントは大蛇丸と周馬の争い。大蛇丸対周馬戦が、チャンバラで行われているところに、雑魚対応ということで針木太郎らが攻め込む。大蛇丸と周馬は、最後、大蝦蟇と大蛇に変身して対峙するんだけど、当然、三すくみの構造からいって、主人公が危うくなっちゃう。そもそもライバルに構造的に勝てない主人公というのもどうかと思うんだけどね、ああもうだめだ、ってところで綱手がやってきて、3匹そろい踏み。三すくみっていったって、そのうち2つが手を組んでいればね、とりあえず相手は退散するしかないでしょう。大蛇丸は逃げ出す。主人公カッコ悪ー。悪悪だね。もう。この手の映画としては致命的ですな。はっはっは。雑魚キャラもとりあえずは何かやってて、深雪は、高遠弓之助の助けを得て、願人太郎を倒し、父の敵を討つ事ができましたとさ。めでたしめでたしと。
 あーようやく終わった、と思った人、いや、手を上げろとはいってないぞー。全員手を上げるなんて、それはなんかの体操かー。体育の授業じゃないぞー。はっはっは。とにかく、終わったと思った人、残念でした。この映画にはしっかり続編があるんだなー。ヤダッて言ってもあるもんはあるんだ。これはお話しないとね、終われないでしょ、普通。さあ、ここで続編の題名をご紹介しましょうぅっっ!「逆襲大蛇丸」!駄目だ。題名からなってないねー。なんだか蛇の方がメインになっちゃってるよねー。
あーようやく終わった、と思った人、いや、手を上げろとはいってないぞー。全員手を上げるなんて、それはなんかの体操かー。体育の授業じゃないぞー。はっはっは。とにかく、終わったと思った人、残念でした。この映画にはしっかり続編があるんだなー。ヤダッて言ってもあるもんはあるんだ。これはお話しないとね、終われないでしょ、普通。さあ、ここで続編の題名をご紹介しましょうぅっっ!「逆襲大蛇丸」!駄目だ。題名からなってないねー。なんだか蛇の方がメインになっちゃってるよねー。 話はあんまり変わんない。鯨波の殿様がうなされてるところから。児雷也が現れてからよく眠れないようだ。まあそりゃそーだろーねー。どんなに警備しててもフリーパスで入ってくる人間に命を狙われてるんだから。夢から覚めるとほんとに児雷也がやってきていて、適当にみんなを脅かして去っていく。
話はあんまり変わんない。鯨波の殿様がうなされてるところから。児雷也が現れてからよく眠れないようだ。まあそりゃそーだろーねー。どんなに警備しててもフリーパスで入ってくる人間に命を狙われてるんだから。夢から覚めるとほんとに児雷也がやってきていて、適当にみんなを脅かして去っていく。一方、諏訪家では、児雷也の扱いについて評議をしている。弓之助の提案により、鎌倉管領足利家に申し出て、尾形家再興ならびに鯨波家追討の令状を受けることになる。弓之助が使者となって、鎌倉に行く。 児雷也の隠れ家では、諏訪家と協力するよう求める深雪や綱手の説得に耳を貸さない児雷也がいた。
鎌倉帰りの弓之助一行。首尾よく鎌倉管領家から令状をもらっている。つり橋に差し掛かったところで突然の稲光が。橋だと思ったのは、実は大蛇丸が変化したもので、弓之助らは落ちてしまう。大蛇丸らは、弓之助らを身ぐるみ剥いで川に投げ込む。川に流された弓之助を児雷也が助ける。
一方で諏訪家の家老高遠多聞助、あ、これは弓之助の父親なんだけど、鯨波家に赴いて、諏訪と鯨波の婚礼を破談にするよう申し入れている。そこに、もう一人の多聞助が。実は、こちらは大蛇丸が変身したもの。大蛇丸は弓之助から奪った令状を持って、鯨波家に諏訪家のたくらみをばらしに来たわけ。多聞助は捕らえられる。鯨波家としては、児雷也に狙われている以上、どうしても大蛇丸の協力がほしい。そこで大蛇丸が出した条件は、宝刀朝霧丸と、全国の山の支配権だったと。鯨波家は、朝霧丸を手に入れるため、女盗賊に依頼する。
大蛇丸と女盗賊は協力して諏訪家の城に侵入して、大蛇丸は諏訪の姫を、女盗賊は朝霧丸を持って大蛇丸を撃退しようとしていた深雪を朝霧丸とともにさらう。鯨波家は諏訪家の裏切りに怒り大軍をもって攻め寄せる。当初は鯨波家の大勝で、戦勝祝いをしているところに、児雷也乱入。追討令状を奪い返す。
追討令状を手に入れた児雷也ではあるが、これをもって諏訪家と協力して鯨波家を撃とうという針木太郎や綱手の言うことはきかず、あくまで諏訪と鯨波が互いに争って互いに傷つくことが復讐になると言い張る。そこに女盗賊がやってきて、児雷也に朝霧丸を渡すという。児雷也は綱手が止めるのも聞かず、女盗賊についていってしまう。
女盗賊と児雷也の中を疑った綱手が嫉妬心を持ったら、なぜか蛞蝓の術が失われて、諏訪の姫と綱手は敵に捕まってしまう。それで、綱手が閉じ込められるところが塩蔵!蛞蝓の術を会得したものは、塩に弱いらしいですよ。覚えておこう。試験に出るよ。数学の。はっはっは。一方女盗賊についていった児雷也も、罠にかかって捕まってしまう。
 諏訪の城の目の前で、児雷也の処刑を執り行う鯨波。すると、諏訪家の面々が、城を明け渡すかわりに児雷也の助命を願う。これを聞いた児雷也の心がうごく。単純なやっちゃで、ホンマ。なぜ関西弁っていわれてもねー。こういうときは関西弁でしょ。フツー。理由?理由なき反抗。ジェームズ・ディーンみたいって言われたことはないけどね、先生はひそかに自分は似てると思ってんだよ・・・・世界で一番ジーンズが似合う蛙としてね、もうちょっと認められてもいいかなとね・・・・・人、じゃない蛙の話をきけぇえええええ!!
諏訪の城の目の前で、児雷也の処刑を執り行う鯨波。すると、諏訪家の面々が、城を明け渡すかわりに児雷也の助命を願う。これを聞いた児雷也の心がうごく。単純なやっちゃで、ホンマ。なぜ関西弁っていわれてもねー。こういうときは関西弁でしょ。フツー。理由?理由なき反抗。ジェームズ・ディーンみたいって言われたことはないけどね、先生はひそかに自分は似てると思ってんだよ・・・・世界で一番ジーンズが似合う蛙としてね、もうちょっと認められてもいいかなとね・・・・・人、じゃない蛙の話をきけぇえええええ!!綱手は、塩蔵で力尽きそうになったところを、蛞蝓の精、ああ、最初の映画で術を授けた婆ね、その人が突然現れて、再度綱手に術を授ける。
児雷也が火にかけられて、絶体絶命!というところに、綱手が駆けつける。やっぱり児雷也カッコ悪。首尾よく綱手が児雷也を助けてしまうと、怒った大蛇丸は、逆切れなのかなんなのか、唐突に諏訪の若君を抱えて屋根にのぼり、若君を堀に投げ込んでしまう。若君が落ちた!と思った堀から児雷也が現れ、若君を助ける。諏訪家につくことにしたわけだね。はっはっは。
女盗賊は、大蛇丸に助勢すべく、朝霧丸をとりにアジトへ。後を追った綱手ともみ合い。納得いかないのがこの戦いなんだよね。蛞蝓の術を使える綱手にとってみれば、術を使えば簡単にこの戦いを終わらせられるのに、なんだが普通に争って、最後に短刀で女盗賊を一突き、朝霧丸を手に入れる。
 児雷也は、大蛇丸を追って屋根にのぼり、最後の決戦が始まる。でもねー、当然のことながら、蝦蟇は大蛇に大苦戦。というより、もう戦うな、最初っから、ってぐらい、良いところなくやられる。まさに児雷也が力尽きそうなそのとき、綱手が駆けつけ、朝霧丸で大蛇丸を撃退、って逃げちゃうんだけどね。それで決着。なんとも中途半端な終わりではあるけど、これで終了。
児雷也は、大蛇丸を追って屋根にのぼり、最後の決戦が始まる。でもねー、当然のことながら、蝦蟇は大蛇に大苦戦。というより、もう戦うな、最初っから、ってぐらい、良いところなくやられる。まさに児雷也が力尽きそうなそのとき、綱手が駆けつけ、朝霧丸で大蛇丸を撃退、って逃げちゃうんだけどね。それで決着。なんとも中途半端な終わりではあるけど、これで終了。前作に比べて大分端折った解説になったけどねー。なぜかって?この続編は大蛇丸ばっかでてくんだよ。蛇は嫌いだーぁあああああああああああ!!
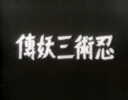 なんかね、蝦蟇の妖術がぜんぜん役に立たない主人公というのはやだね。なんだか、肝心なときは奥さんに面倒を見てもらうヒモみたいだよ。うん。というわけで、今度はもうちょっと主人公がカッコいいやつを選んできました。「自来也 忍術三妖傳」。若いころの片岡千恵蔵が主演している戦前の映画だよ。これはね、良いです。
なんかね、蝦蟇の妖術がぜんぜん役に立たない主人公というのはやだね。なんだか、肝心なときは奥さんに面倒を見てもらうヒモみたいだよ。うん。というわけで、今度はもうちょっと主人公がカッコいいやつを選んできました。「自来也 忍術三妖傳」。若いころの片岡千恵蔵が主演している戦前の映画だよ。これはね、良いです。黒姫城の城主更科輝隆は、家臣の佐久間正盛らの裏切りによって討たれ、その息子太郎丸も、山奥の洞窟に放り込まれる。そこに仙人があらわれ、太郎丸は山にこもって修行することになる。
 20年経って、術が完成した太郎丸は、悪因悪果は自ら来る也、自来也と名乗り、復讐の旅に出る。
20年経って、術が完成した太郎丸は、悪因悪果は自ら来る也、自来也と名乗り、復讐の旅に出る。まずは一味の一人、矢部郡太夫のところ。郡太夫が寝ていると、妙な気配。起き上がってみると、いつの間に書かれたのか屏風に大きく「自来也」の文字!そして蛙が跳んできた。出た!蛙!普通のだけどね。はっはっは。そして郡太夫が蛙を捕まえようとすると、蛙はかき消え、自来也登場。
「恐ろしくば泣け!叫べ!吼えろ!ふっふっふっふっふっ、はぁっはっはっはっは」
これをね、千恵蔵のオーバーで重厚な絶叫で聞かされると、もうこの映画に夢中になること請合い。彼の高笑いには先生も負けるなー。はっはっはっばっげふっごほっがっがっが・・・ああ苦しい。ちょっと無理な笑いしちゃったよ。はっはっは。
郡太夫が倒されたことを知らせる使者が、次の標的五十嵐典膳のところへ来る。使者が人払いを、というので典膳が家来を遠ざけると、おもむろに使者が口上を述べ始める。実は、この使者が自来也!しかし、典膳は逃げ、これを親分の佐久間のところに知らせに行く。佐久間は今や、将軍家守護職にあって、京都におり、自来也もこれを追って京都に向かう。
 途中、若侍に扮して、やっぱり佐久間を敵と狙っている綱手姫に会う。なんだか妙に自来也に絡む綱手。特に理由もなさそうなのに、自来也を好きになってしまったようだね。京都についてとった宿には、大蛇丸がいて、これは綱手を好きになる。綱手に迫ったところ、妙に嫌われ、しかも自来也に邪魔されて、佐久間のところに駆け込み、自来也の居場所を伝えてしまう。そうそう、蛇ってのはこういう姑息で汚い役がピッタリだよ。先生としてはね、やっぱり蛇はかっこ悪くないとね、楽しくないです。蛙としてね。当然というべきだよ。うん。はっはっは。
途中、若侍に扮して、やっぱり佐久間を敵と狙っている綱手姫に会う。なんだか妙に自来也に絡む綱手。特に理由もなさそうなのに、自来也を好きになってしまったようだね。京都についてとった宿には、大蛇丸がいて、これは綱手を好きになる。綱手に迫ったところ、妙に嫌われ、しかも自来也に邪魔されて、佐久間のところに駆け込み、自来也の居場所を伝えてしまう。そうそう、蛇ってのはこういう姑息で汚い役がピッタリだよ。先生としてはね、やっぱり蛇はかっこ悪くないとね、楽しくないです。蛙としてね。当然というべきだよ。うん。はっはっは。 大蛇丸のタレコミを受けて、佐久間は自来也のいる宿を急襲、これを捕らえて牢に閉じ込める。一方綱手は蜘蛛に変じてこの後を追い、佐久間の動向をうかがう。あれ?この映画だと蜘蛛だねー。なんで?蛞蝓じゃないと三すくみにならないじゃん。別にいいのかね。そんなのは。まあ、姫が蛞蝓というより蜘蛛の方がイメージがいいからね、変えたのかな。
大蛇丸のタレコミを受けて、佐久間は自来也のいる宿を急襲、これを捕らえて牢に閉じ込める。一方綱手は蜘蛛に変じてこの後を追い、佐久間の動向をうかがう。あれ?この映画だと蜘蛛だねー。なんで?蛞蝓じゃないと三すくみにならないじゃん。別にいいのかね。そんなのは。まあ、姫が蛞蝓というより蜘蛛の方がイメージがいいからね、変えたのかな。大蛇丸が蜘蛛の正体を見破り、綱手と大蛇丸と佐久間の家来たちの大乱闘になる。一方牢屋に入れられていた自来也も、術を使って簡単に抜け出す。そして、そして、そして、ついに蝦蟇が乱闘場所に登場!これだよこれ。こういうのだよ。こういう術が観たかったんだよ。スンバらしい。


蝦蟇の助けで綱手は大蛇丸を倒す。そして蝦蟇が佐久間の家来の相手を適当にしてる間、あのね、口から家来を吸い込んじゃったりとか、というような相手の仕方なんだけどね。蛙らしくていいね!はっはっは。で、その蝦蟇が相手してる間に、綱手と自来也は、五十嵐典膳と佐久間正盛とチャンチャンバラバラ。二人を討ち取ってめでたしめでたし。もう王道。これ以外の自来也は先生が認めません。まあ世間は認めるかもしれないけどね。はっはっは。

さて、こんな素晴らしい映画はね、実を言うと1956年にリメイクされとります。題名は「妖蛇の魔殿」。主演は同じく片岡千恵蔵。前作から20年近く経ってるのに、まだ20代の役が出来るとは驚異的と思って観たんだけどねー。
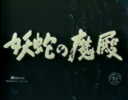

・・・ちょっと無理がありましたねー。はっはっは。しかもあの素晴らしい大蝦蟇が出てこないし。最後にちょこっとシルエットで登場するだけだし。名作をリメイクしちゃいかん、という好例ですよこれは。
と、今回は一気に4本紹介してみました。お、いかんいかん。授業の時間を大分過ぎてしまいましたねー。はっはっは。皆机に突っ伏してなにしてんだー!あれ?反応がないな。誰かなんか言えー!感想はどうだ感想は。・・・・なんだ全員寝てんのか。しょーがないなまったく。先生のこの素晴らしい講義を聞かないとはね・・・。まあいいや、とりあえず、総括しときましょう。蛙的にいうと、自来也ものは、「自来也 忍術三妖傳」で決まり。ほかは観んでいい。以上。
さーてと。まだ皆寝てるよーだなー・・・・・・・・・全員落第っと。・・あれ?起きた?冗談冗談。はっはっは。